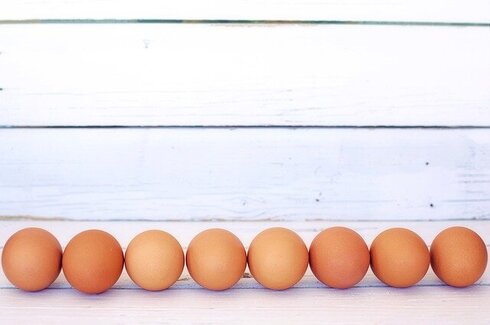糖尿病合併 動脈硬化 を医学的に防ぐ対策と危険な指標をまとめています。「動脈硬化」という言葉は、いまではとても耳に馴れた、なじみ深い言葉の1つです。
動脈という、心臓から全身に酸素を送る血管が硬くなったり、厚くなったりして血のめぐりが悪くなったり、血管が詰まった状態を総称して、「動脈硬化」といいます。
糖尿病合併 動脈硬化を防ぐための医学的対策
糖尿病患者における動脈硬化(大血管症)を予防するためには、血糖管理に加えて、他の主要な危険因子を包括的に管理することが不可欠です。
1. 血糖コントロールの徹底
- 目標設定: 血糖が高い状態が続かないよう、一般的にHbA1c 7.0%未満を目指します。ただし、個々の状態(年齢、合併症、治療法)に応じて目標値は主治医と相談して決定します。
- 薬剤治療: 食事・運動療法で目標達成が難しい場合は、インスリンやGLP-1受容体作動薬、SGLT2阻害薬などの血糖降下薬を用いて厳格に血糖を管理します。
2. 血圧の厳格な管理(高血圧対策)
- 目標設定: 動脈硬化の進行を防ぐため、血圧を130/80 mmHg未満に管理することが推奨されています。
- 薬剤治療: 食塩制限などの生活習慣改善に加え、ACE阻害薬やARBなどの降圧薬を適切に使用し、血圧を目標値まで下げます。
3. 脂質異常症の是正
- 目標設定: LDLコレステロール(悪玉コレステロール)の厳格な管理が必須です。心筋梗塞・脳卒中の既往がある高リスク群ではLDL-C 100 mg/dL未満、特にリスクの高い超高リスク群では70 mg/dL未満など、リスクレベルに応じて目標値が設定されます。
- 薬剤治療: スタチン薬が中心的な治療薬となり、必要に応じて他の脂質改善薬を併用します。
4. 生活習慣の改善(非薬物療法)
- 禁煙: 喫煙は動脈硬化を悪化させる最大の要因の一つであり、完全な禁煙が必須です。
- 食事療法: 栄養バランスを整え、特に塩分摂取量を1日6g未満(または個別の目標値)に抑えます。飽和脂肪酸やコレステロールの過剰摂取を控え、野菜や魚の摂取を増やします。
- 運動療法: 中等度以上の有酸素運動を毎日合計30分以上を目安に行い、内臓脂肪型肥満の解消を目指します。
5. 抗血小板薬の検討
- 心筋梗塞や脳卒中をすでに発症した患者(二次予防)に対しては、再発予防のために低用量アスピリンなどの抗血小板薬が使用されます。発症前の患者(一次予防)への投与は、出血リスクなどを考慮し、個別に判断されます。
危険な指標(動脈硬化リスクを示す検査値)
動脈硬化の進行やリスクの高さを示す、特に注意すべき検査値と目安は以下の通りです。これらの値が目標範囲から外れている場合、積極的な対策が必要です。
1. 血糖関連指標
- HbA1c: 7.0%未満が一般的な目標です。高値は、動脈硬化を含む糖尿病合併症のリスクを総合的に高めます。
2. 血圧指標
- 血圧: 130/80 mmHg未満が目標です。高血圧は血管壁に物理的な負荷を与え、動脈硬化を直接的に促進します。
3. 脂質関連指標
- LDLコレステロール(悪玉): 100 mg/dL未満(リスクにより異なる)。高値は血管壁へのコレステロール沈着を促進します。
- Non-HDLコレステロール: 130 mg/dL未満(リスクにより異なる)。LDL-Cに加え、他の動脈硬化促進性リポ蛋白のコレステロールを含むため、中性脂肪が高い場合に重要です。
- 中性脂肪 (TG): 150 mg/dL未満。高値は動脈硬化のリスクを高めます。
- HDLコレステロール(善玉): 40 mg/dL以上。低値(40 mg/dL未満)は動脈硬化のリスク因子の一つです。
4. 肥満関連指標
- BMI (Body Mass Index): 25 kg/m²未満が目標です。肥満(特に内臓脂肪型)は糖尿病、高血圧、脂質異常症を悪化させ、動脈硬化を促進します。
5. 血管評価指標
- ABI (Ankle Brachial Index): 足首と上腕の血圧の比率で、0.9以下は末梢動脈疾患(PAD)の進行を示し、全身の動脈硬化の危険なサインです。
- 頸動脈超音波検査: 頸動脈のIMT(内膜中膜複合体厚)の肥厚やプラークの存在は、全身の動脈硬化の進行を示す危険な所見です。
糖尿病合併 動脈硬化 を医学的に防ぐ対策と危険な指標
ガンより怖い糖尿病ということで衝撃を受けたのですが、実はその糖尿病を上回る危険度の高い病気が「動脈硬化」だというところに行き着きました。
どうやったら動脈硬化を防げるのかを医学的側面から見てみました。動脈硬化の最大の危険国子は糖尿病です。 糖尿病を合併している方もいると思いますが、その場合どうしたらいいのでしょうか?
糖尿病より怖い動脈硬化 コンテンツ
- 日本人は脳卒中を起こしやすい体質
- 脳卒中は、破れる」から「詰まる」へ
- 脳卒中は1つのリスクで発症する
- LDLとHDL比
- 糖尿病はありとあらゆる指標の値が猛スピードで悪化していく
- プラークが意味するもの
- 食べたものが血管に与える影響について
- 自分の動脈硬化の現状
- 塩分の過剰な摂取がなぜ血圧を上げてしまうのか?
- 生命に大きく関わる「動脈硬化」とは?
- 動脈硬化の最大の危険国子は糖尿病
- やや高めに推移している値には危険がいっぱい
動脈硬化 関連ページ